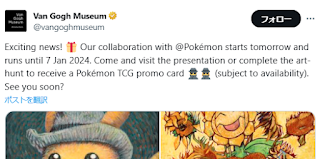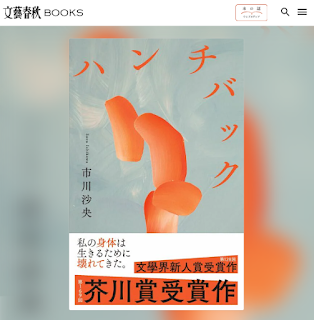【能登半島地震】熊本市現代美術館が残した道しるべ|リットVRギャラリー

メディアが伝える能登半島地震と熊本地震の違い 令和6年 能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県。2024年2月26日現在、240名を上回る人命が失われ、現在も1万人を超える人々が避難生活を余儀なくされています。 能登半島地震8週間 1万人超が避難所で暮らす 支援継続が課題に|NHK また、インフラの復旧も過去の地震災害に比べ進んでいないとの報道も数多くなされています。2024年2月1日付の朝日新聞デジタルの記事では、2016年に発生した熊本地震との被害状況や復旧状況のデータをグラフ化しており、グラフの差異から今回の能登半島地震では実態把握や復旧に多くの時間を要していることがよくわかります。 長期化する断水・通行止め…復旧なぜ進まない?遅れをグラフ化|朝日新聞デジタル 数々の要因が重なり復旧が進まない困難な状況はあるかと思いますが、復旧に関わる皆様のご尽力に感謝しつつ、被災地の1日も早い復旧をお祈り致します。 熊本地震における美術館・博物館の被害と復旧時期 当ブログでは、石川県内で現在休館されている美術館・博物館の早期の復旧と再開館を注視し、能登半島地震後、公式サイトや公式SNSで公表されている石川県内の美術館・博物館の開館状況を可能な限りまとめてまいりました。 石川県内の美術館・博物館の開館状況|リットVRギャラリー 一方で未だ再開館が見通せない石川県内の美術館や博物館も数多くある中、朝日新聞デジタルのニュースで能登半島地震と比較された熊本地震では、美術館・博物館がどのような被害を受け、どのような時期に復旧・再開できたのでしょうか? 当ブログでは、Webのアーカイブを中心に調べてみました。 ※2016年当時の熊本地震で被災した美術館・博物館のWebニュースが辿れないため、公式サイトや外部記事、収支報告書などを元に記載しております。 ・熊本市現代美術館 公式サイト https://www.camk.jp/ 被害:内部設備に被害、展示品の落下など被害 休館期間:2016年4月16日~6月25日(参照: 熊本地震記録集「地震のあとで」 ) 修復費:548万円( 公益財団法人熊本市美術文化振興財団の収支報告書より ) ・熊本県立美術館 公式サイト https://www.pref.kumamoto.jp/site/museum/ 被害:内部設備に...